この記事では、最近私がAIとシステム開発について考えていること、特にAIの便利さを享受しつつも感じている危機感と、それに対してどのように自分のキャリアを考えていくべきか、という現時点での考えを整理し、共有することを目的としています。
AIの進化と私の開発現場:生産性向上と忍び寄る危機感
私はアプリ・システム開発を生業にしていますが、最近は特にAIの便利さにものすごく助けられていると感じています。
例えば、朝何かアイデアを思いついた時、AIと壁打ちしながら設計を進め、ある程度考えがまとまったら実装に取り掛かることで、1日で動くものが作れることもあります。
これによって、自分が本当に作りたいと思ったものや、以前は手間や学習コストが気になっていたような、しっかりとした設計に基づいた開発も、より気軽に実現できるようになったと感じています。
「できること」のハードルがぐっと下がった感覚があり、作成するファイルが多くて途中でモチベーションが続かなくなってしまう、なんてことも少なくなりました。
おかげで、休日や帰宅後の個人的な開発作業も、以前よりずっと捗るようになりました。
こいつがあと2年早くあれば、あんなに働き続けることもなかったのにと感じてます。
もちろん、AIが万能というわけではなく、うまくハマらない場合は地道に自分で実装することもありますが、それでも全体的な生産性は、体感で50%以上は向上したように感じています。
特に、0から1を生み出す部分や、0から10くらいまでの初期段階、あるいは30から70くらいまで開発が進んだ状態からさらに進めるような場面では、4〜5倍くらいの生産性向上を実感することもあります。
ただ、このような状況に甘んじて油断していると、将来的に仕事がなくなってしまうのではないか、考える力が下がるのではないか、
という強い危機感も同時に感じています。
人間の役割はどこへ? AI時代の開発プロセス変化への懸念
具体的には、設計、ドキュメント作成、コーディング、そしてテストの実装といった作業のコストが明らかに下がっていて、場合によってはAIに実装させた方が、変な癖のない成果物が出来上がることもあります。
こうなってくると、人間が主に担当する領域は、プロジェクトの上流工程(要求定義や要件定義など)や、リリース後の運用・メンテナンスといった、いわば開発プロセスの両極端に位置する部分に集約されていくのではないかと感じています。
例えば、これまでコーディングが好きで、その技術やテクニックを熱心に磨いてきた方々にとっては、その専門性を活かせるポジションが、今まで以上に競争の激しいものになるのではないかと懸念しています。
正社員であれば、すぐに解雇されるといったことは少ないかもしれませんが、特にパートナー企業の社員の方や派遣、協力会社の社員の方で、主にコーディングとテストだけを担当しているというような立場の方は、より一層危機感を持った方が良いのかもしれない、と私は考えています。
AIエージェントが活躍する未来の開発フロー(想像)
今後、開発プロセスは例えばこんな風に変わっていくかもしれません。もうすでに変わっているかもしれません。
- 一部の専門知識を持った人間が、お客様や関係者(ステークホルダー)との間で要求定義を行います。
- 次に、その要求を基に、AIエージェントを活用しながら要件定義を進めていきます。
- そして、ステークホルダーと開発範囲(スコープ)について議論し、期待値を調整します。
- その後、再び一部の専門知識を持った人間が、AIエージェントを駆使して設計から実装、テストまでを一気通貫で行い、
- 最終的に受入テストを経て本番導入、そして運用へと移行していく…という流れです。
もしこのような流れが主流になった場合、明確な強みや訴求ポイントがなければ、社外のエンジニアの方がプロジェクトに参画できる機会は、今よりも見つけにくくなってしまうのではないかと懸念しています。
企業の内製化と成長スピードの格差
このような状況を考えると、これからは各企業が、社員自身の手でAIなどの新しい技術を活用しながらシステム開発を行い、それを自ら運用し、継続的に改善していくというサイクルを回していくことが、ますます重要になってくると私は考えています。
例えば、
- A社: AIを積極的に活用しながら自社内で開発サイクルを高速に回し、運用・改善を通じて社内にノウハウ(ナレッジ)を蓄積し、成長していく。
- B社: 従来通り外部のベンダー企業に開発を委託し、数ヶ月かけて稟議を通し、フェーズごとに区切って開発を進め、本番化に至る。そして、しばらく経ってからベンダーの営業担当者から改善提案を受ける…。
私自身も以前はベンダー企業に勤めていた経験があるので、ベンダーの役割を否定するつもりは全くありません。それぞれの立場や役割があることは理解しています。ただ、発注者側が期待するような成長スピードという観点では、従来のベンダー依存の体制では、AIを活用した内製化を進める企業に比べて、どうしても差が出てきてしまうのではないかと感じています。
特に、AI技術の進化のスピードは驚くほど速いですから、この成長速度のギャップは、A社とB社のような企業間で、今後ますます大きくなっていくのではないかと私は予測しています。
AI時代を生き抜くための生存戦略を考える
これから先、世の中が具体的にどうなっていくのかを正確に予測することは非常に難しいのですが、少なくとも現時点で私が考えているのは、もしあなたがシステムベンダーやSESといった業界で仕事をしているのであれば、AIという存在に対して真剣に危機感を持ち、自分自身の生存戦略を今からしっかりと考えていく必要があるのではないか、ということです。
もし、あなたが心からアプリを作ることが好きなのであれば、その「開発者」というポジションを、形は変わるかもしれませんが、これからも維持し続けられるように、今から行動していくことが大切だと感じています。
私が目指したいありたい姿
では、具体的にどのような「ありたい姿」を目指すべきでしょうか? 私の場合は、次のようなことを考えています。
- まず、生活していくためにも、しっかりとお金を稼ぐこと。
- そして、何よりも、これからも大好きなシステム開発の仕事に携わっていくこと。
そのために目指すべきは、AIに対して的確な指示を出し、AIが生成した結果の品質や妥当性を適切に判断、
適切な問いから問題を決め課題(テーマ)を立て、解決や完了まで進めること。
と考えています。
これから起こりうること、その中での戦略案(妄想含む)
- ベンダー内のエンジニアのスキルレベルの均一化: AIの活用が進むと、アウトプットの最低ラインが底上げされるかもしれません。
- AIエージェントの開発・導入支援という新たなビジネス: ベンダー企業自身が独自のAIエージェントを開発したり、その導入支援サービスを提供したりする、といったビジネスモデルも出てくるかもしれません。
- AIによるテスト自動化と品質向上: 例えば、ユニットテストの作成をAIに任せることで、開発するシステムの品質向上にも繋げられるでしょう。
- 受注量・担当範囲の拡大: 結果として、企業としてはより多くの案件を受注できるようになり、エンジニア一人ひとりが担当できる顧客の範囲や作業量も増えていく可能性があります。
- AIを使わない選択肢はほぼなくなる: もはや、これからの時代、AIを使わないという選択肢は、ほぼ無くなっていくのではないでしょうか。
- ずっと忙しい: AIが大量のアウトプットを持ってくるので、常にレビューし続けないといけなくなり忙しくなるのではないでしょうか。
- 実力以上の成果物責任: AIが作った成果物が難しくて理解できない、レビューできない。AIが作ったから大丈夫・AIが作ったので思考停止で採用する。といった責任面で問題が起きるかもしれません。
- (ベンダー内のエンジニアのスキルレベルの均一化に関して)これは、ユーザーの視点から見れば非常に歓迎すべきことだと思います。
- より上流の工程に関与していくことが重要になると考えています。
- アウトプット量の増加による単価維持: 何もしなければ個人の単価は下がってしまう恐れがあります。それを避けるためには、AIを活用して一人当たりのアウトプット量を増やし質を上げる、という方向性が考えられます。

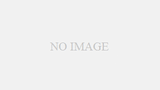
コメント