問題や課題の定義
- 問題とは、現状とあるべき姿(ありたい姿)とのギャップ。
- 課題とは、ギャップを埋めるステップや対応するべき事項。
深掘りのプロセス
1) 現状とあるべき姿のギャップ抽出。
2) SWOT分析。
3) SWOT分析からクロスSWOTで戦略をピックアップ。特にWO戦略、WT戦略をメインに。
4) 上記3)をなぜなぜ分析し、これ以上掘れないところまで深掘りする。それを3つぐらい用意。
5) 上記4)を抽象化したものをピックアップ。
6) 上記5)が根本の問題になる。
7) 上記4)が課題なので、これを対応するスケジュールをゴールから逆算で作成。
8) 実施・ふりかえり・改善を行いモニタリングする。
AIに評価してもらい、新しい分析プロセスを蒸留してみる。
新しい分析プロセスの評価と改善提案
AIからの評価
点数は80点ぐらい。下記評価だった。
- 戦略的視点の導入:SWOT→クロスSWOT(特にWO/WT)で環境適応や弱点克服の方針を明確化
- 深掘りの徹底:なぜなぜ分析で「これ以上掘れない」レベルまで原因を追究
- 抽象化による本質抽出:深掘りした要因を抽象化し、複雑な事象から核心となる問題を定義
- プロセスの一貫性と具体性:ギャップ抽出からPDCAまでの流れが連続しており、深掘り結果に基づく課題設定で実行計画に落とし込みやすい
マイナスポイントとしては、戦略をなぜなぜ分析しているがやや回りくどい。混乱を招く可能性がある。
強みを活かす方向も模索する必要があるのではないかでした。
改善点、代替案
よりシンプルで効果的な流れにするための改善。流れは下記になりました。
- 問題の明確化
- 環境分析(オプション)
- 根本原因分析(深掘り)
- 課題の設定
- 解決策(戦略/打ち手)の立案と選定
- 実行計画の策定
- 実行・モニタリング・評価・改善
1. 問題の明確化
現状(As Is)とあるべき姿(To Be)を定義し、ギャップ(=問題)を具体的に特定する。
2. 環境分析(オプション)
SWOT分析を行い、問題を取り巻く外部環境(機会・脅威)と内部環境(強み・弱み)を把握する。(※省略または後工程でも可)
3. 根本原因分析(深掘り)
ステップ1で特定した問題(ギャップ)に対して、
「なぜなぜ分析」「ロジックツリー」「特性要因図」などを用いて、根本原因(=本質的問題)を特定する。
深掘りの対象を「問題(ギャップ)」または「その要因」へ
現状: 「戦略」を深掘り。
提案: ステップ1で抽出した「ギャップ(問題)」、またはそのギャップを引き起こしていると推測される「要因(仮説)」に対して、
直接「なぜなぜ分析」や「ロジックツリー」を適用します。
理由: これにより、問題の根本原因(=本質的問題)により直接的に、かつ効率的にアプローチできます。
SWOT/クロスSWOTの活用タイミングの最適化
現状: 問題抽出後にSWOT/クロスSWOTを行い、その戦略を深掘り。
提案:
案A(原因分析後に活用): 問題の根本原因を特定した後、その原因を解決するための「解決策(打ち手、戦略)」を立案する段階で、クロスSWOT分析(SO, ST, WO, WT全てを考慮)を活用します。これにより、特定された根本原因に対して、自社の内外環境を踏まえた最適な戦略を選択・設計できます。
案B(問題分析の初期段階で活用): 問題(ギャップ)を特定した後、SWOT分析を行い、問題を取り巻く環境(機会、脅威、強み、弱み)を理解します。これを踏まえて、根本原因分析(なぜなぜ分析など)を進めることで、より多角的な視点で原因を探ることができます。クロスSWOTはこの段階で行わず、解決策立案時に活用します。
理由: SWOT/クロスSWOTは、原因そのものを特定するよりも、環境分析や戦略オプションの生成・評価に強みを持つツールであるため、適切なタイミングで活用することで効果を最大化できます。
4. 課題の設定
特定した根本原因(本質的問題)を解決するための、具体的で測定可能な課題を設定する。
「根本問題」と「課題」の定義を再整理
根本問題(本質的問題): 問題(ギャップ)を引き起こしている、これ以上深掘りできないレベルの根本的な原因。
課題: 根本問題を解決するために取り組むべき、具体的で測定可能な目標やテーマ。
理由: この定義により、目指すべき方向性(根本問題の解決)と、そのための具体的なステップ(課題)が明確になり、行動計画に繋がりやすくなります。
5. 解決策(戦略/打ち手)の立案と選定
設定した課題を達成するための具体的な解決策を複数立案する。
ここでクロスSWOT分析(SO, ST, WO, WT)を活用し、内外環境を踏まえて最も効果的で実行可能な解決策(戦略)を選択・優先順位付けする。
6. 実行計画の策定
選択した解決策について、具体的なタスク、担当者、期限、KPIなどを明確にした実行計画を作成する。(ゴールから逆算する手法は有効)
7. 実行・モニタリング・評価・改善
計画を実行し、進捗と結果をモニタリング。定期的に振り返りを行い、必要に応じて計画や行動を修正する。
graph TD
subgraph 問題分析フェーズ
A["1.問題の明確化<br/>現状(As Is)と<br/>あるべき姿(To Be)の<br/>ギャップを特定"] --> B("2.環境分析<br/>※オプション<br/>SWOT分析などで内外環境を把握");
B --> C["3.根本原因分析(深掘り)<br/>ギャップ/要因に対し<br/>なぜなぜ分析、ロジックツリー等で<br/><b>根本原因</b>を特定"];
C --> D["4.課題の設定<br/>根本原因を解決するための<br/>具体的・測定可能な<b>課題</b>を設定"];
end
subgraph "解決策立案・実行フェーズ"
D --> E["5.解決策(戦略/打ち手)の立案と選定<br/>課題達成のための策を複数立案<br/><b>クロスSWOT分析</b>などを活用し<br/>最適な策を選択・優先順位付け"];
E --> F["6.実行計画の策定<br/>タスク、担当、期限、KPIを設定<br/>(ゴールから逆算)"];
F --> G["7.実行・モニタリング・評価・改善<br/>計画実行と進捗確認<br/>定期的な振り返りと修正"];
end
style B fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#333
style C fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#333
style E fill:#cfc,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#333
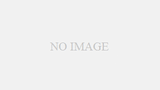
コメント