この記事は、結果ばかりにとらわれていた私が、過程や周囲への影響を重視する考え方へと変わっていった経験と、その変化を後押ししてくれた古くからの教えについて共有するものです。同じように悩んでいる方の、何か少しでもヒントになれば嬉しいです。
きっかけは日々の悩みから
最近、私の考え方は大きく変わりつつあります。
以前は「目標を達成できたか?」「数字はどうか?」といった「結果」ばかりを気にしていました。
でも、どんなに努力しても、結果には運やタイミング、自分ではどうにもならない外部の要因が大きく絡んできますよね。それに一喜一憂することに、少し疲れを感じ始めていたんです。
もし、望んだ結果が出なかったら、それまでの頑張りや費やした時間が全て無駄になってしまうような感覚。これって、なんだかとても窮屈だと思いませんか?
例えば、こんなことを通勤中にぐるぐると考えていました。
- 仕事で大きな目標を掲げて、チーム一丸となって遅くまで頑張っても、ほんの少し目標に届かなかったら、その努力は無意味だったのか?
- 多少無理をしてでもシステムを開発し納品したのに、不具合が出たら「使えないシステムだ」と一蹴され、関係者へのヒアリングや学んだことまで否定されてしまうのか?
- 子どもが学校で嫌なことを言われて、つい手が出てしまった。だからといって、これまでの子育てや、築いてきた親子関係、友人関係まで全部が無駄だった、なんてことになるのだろうか?
こんな風に、何日も同じようなことで悩み、答えが出ないループに陥っていました。
このままではいけない。この堂々巡りから抜け出すために、意識して自分の考え方を変えていこうと決意しました。
そして気づいたのは、本当に大切なのは「自分がどれだけ全力を尽くして行動し、その過程を楽しみ、周囲にポジティブな影響を与えられたか」ではないか、ということでした。
古くからの教えにヒントがあった
この「過程重視」の考え方、実は調べてみると、古くから存在することに気づきました。いくつか、私の背中を押してくれた教えを紹介します。
ヒンドゥー教の『バガヴァッド・ギーター』が説く「カルマ・ヨーガ」
これは、「自分のなすべき行為(全力で取り組むこと、貢献すること)には責任を持つ。しかし、その結果(成功や失敗、報酬など)には執着しない」という姿勢を教えてくれます。行為そのものに誠実であること、その純粋な動機に価値を見出す考え方です。
ストア派哲学
ストア派の哲学者たちは、私たちが本当にコントロールできるのは「自分の意志、判断、そして行動(どう全力を尽くすか、どう周りと関わるか)」だけだと説いています。結果のようなコントロール外のことに心を乱されるのではなく、自分のコントロールできる範囲で最善を尽くすこと(徳の実践)に集中することで、心の平静を得られる、と。
仏教
仏教では、苦しみの根本原因の一つは「結果への過度な執着」にあるとされています。全ての物事は様々な要因(縁)が絡み合って生じる(縁起)と理解し、正しい意図を持って行動することに集中しつつ、その結果は柔軟に受け止める、という考え方です。
私がたどり着いた指針
これらの教えと、私自身の気づきを合わせると、次のような指針が見えてきました。
- 自らの「行為」には主体的に責任を持ち、全力を尽くす。特に、その過程での努力と、周囲へのポジティブな影響を大切にする。
- 一方で、その先にある「結果」は、自分だけでコントロールできるものではないと理解し、過度に執着せず、学びや次への糧として柔軟に受け止める。
この姿勢でいることで、こんな良いことがあると感じています。
- 結果に左右されず、自己成長を着実に実感できる。
- 「やりきった」という感覚が、次へのモチベーションにつながる。
- コントロールできないことへの悩みから解放され、精神的な安定を得やすい。
- 全力で取り組む姿が、自然と周囲に良い影響を与え、信頼や協力関係を築ける。
- 目先の数字だけでなく、本質的な満足感や納得感を持って日々を過ごせる。
- 何よりも、他人や外部環境ではなく、「自分自身」にフォーカスできる。
おわりに
もちろん、結果を完全に無視するわけではありません。結果は、自分の取り組みを振り返り、改善するための大切なフィードバックです。
ただ、それを絶対的な評価基準にするのではなく、「全力で取り組んだ過程」や「周囲への貢献」といった、自分自身でコントロール可能な価値基準をしっかりと持つこと。
この考え方の変化は、私にとって大きな一歩です。もし、あなたが過去の私と同じように結果に縛られて苦しさを感じているなら、少し視点を変えて「過程」や「影響」に目を向けてみるのも良いかもしれません。
私もまだ探求の途中ですが、この価値観を大切にしながら、毎日を過ごしていこうと思います。

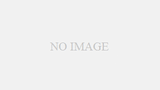
コメント