現状
隔週でチームでふりかえりを行っていて、スプリント計画のストーリーがどの程度達成できたか?大きな課題が起きて妨げになっていないか?チームで共有したい情報を確認しています。その他にも、定量評価項目を確認しています。
チームで現在地を確認し、スプリント内で決めた目的地とのギャップを見ています。
私としては、メンバーの自律性や成長を促すために、施策を考えたり、ファシリテーションで工夫したりしています。
ちょっとした悩み
メンバーの自律性や成長を促すために「ぼかした」表現で問いかけを準備しています。
ふりかえりのアジェンダやドキュメントには具体的な自分の想いは書かずに、記憶に頼って進めています。
なぜなら、自分のPC画面を大きなディスプレイに映しているため、自分用のカンペファイルを開いて見るわけにもいかないからです。
直前まで『この流れで進めて、これを言おう!』と決めて臨んでも、話が盛り上がってくると、進めているうちに忘れてしまうことがあります。
ファシリテーションに集中すると、事前に考えていた細かな言い回しや、伝えたいポイントが飛んでしまいがちです。
改善案
- 記憶に頼るのではなく、「思い出すための仕掛け」 を作ること。
- 問いかけの方法を調査し、深掘りすること。
- ファシリテーションのやり方や型を身につけること。(集中しすぎる課題への対策として)
- ツールを活用すること。
単純に手元に「カンペ」を用意する
詳細な文章ではなく、議論を促したいポイントや問いかけの「キーワード」だけを箇条書きにした紙を手元に用意する。
大きな文字で書いたり、色分けしたりして見やすくする。
例: 「〇〇の連携は?」「ボトルネック?」「設計書の〇〇について深掘りは?」「次のアクションは?」など。
これにより、記憶への負荷が減り、ファシリテーションにより集中できるようになるはずです。
メンバーに詳細な意図を悟られずに、議論の方向性をガイドしやすくなるのではないかと考えています。
アジェンダや資料の表現を少し具体的にする
「ぼかす」意図は保ちつつ、議論の「きっかけ」となる問いやテーマをアジェンダに明記します。
完全に白紙にするのではなく、「今回のふりかえりテーマ案」としていくつか提示する形です。
例: ×「最近のプロセスについて」
〇「最近のスプリントで『スムーズだったこと』『少し引っかかったこと』は?」
アジェンダを見れば、話したかったテーマを思い出しやすくなると思います。
何で問いかけるの?
- 思考の活性化: 問いはメンバーに立ち止まって考えさせ、普段意識していない側面にも目を向ける機会を与えられる。
- 多様な視点の抽出: 異なる視点からの意見やアイデアを引き出し、より本質的な議論を可能にします。
- 主体性の促進: 「答え」を与えるのではなく問いかけることで、メンバー自身が考え、解決策を見出すプロセスを支援できる。
- 心理的安全性の醸成: 適切な問いかけは、安心して意見を言える心理的安全性を作れる。
- 学習と改善のサイクル: 出来事を振り返り、原因を探り、未来のアクションに繋げる一連のサイクルを作ることが可能になる。
問いの種類
- オープンクエスチョン
- クローズドクエスチョン
- 内省を促す質問
- 未来志向の質問
- 仮説を探る質問
- 関係性を問う質問
- 視点を変える質問
議論を促す問いかけテクニック
- 直接的な原因追及を避ける:
- ×「なぜ失敗したのですか?」 → 〇「その結果に至った背景には何があったのでしょうか?」
- ×「誰の責任ですか?」 → 〇「この状況から私たちが学べることは何でしょうか?」
- 狙い: 犯人探しではなく、状況理解と学びを促し、心理的安全性を保ちます。
- 感情や感覚、印象に焦点を当てる:
- 〇「今回のスプリントで、心が動いた瞬間はありましたか?」
- 〇「作業していて『スムーズだな』と感じたのはどんな時でしたか?」
- 〇「逆に『少し引っかかるな』と感じたのはどんな部分でしたか?」
- 狙い: ロジックだけでなく、個人の感覚的な部分を引き出すことで、潜在的な課題や良かった点に気づきやすくなります。
- 抽象度を上げた問いから始める:
- 〇「最近のチームの雰囲気について、どう感じていますか?」
- 〇「今回のリリースで、全体としてどんな印象を持ちましたか?」
- 狙い: まずは話しやすい大きなテーマから入り、徐々に具体的な内容に深掘りしていくことができます。
- 可能性や選択肢を探る:
- 〇「他にどんな考え方やアプローチがありそうでしょうか?」
- 〇「もし〜だとしたら、どんな可能性が考えられますか?」
- 〇「これを別の方法で行うとしたら、どんなアイデアがありますか?」
- 狙い: 思考を広げ、固定観念にとらわれない多様なアイデアを引き出します。
- 肯定的な側面にも光を当てる:
- 〇「今回、特にうまくいったことは何でしたか? それはなぜだと思いますか?」
- 〇「チームメンバーに感謝したいことはありますか?」
- 〇「自分自身の貢献として誇れることは何ですか?」
- 狙い: ポジティブな側面に目を向けることで、チームの強みや成功要因を認識し、モチベーションを高めます。
心構え・注意点
- 聴く姿勢: メンバーの発言を注意深く聴くことが重要です。相槌や言い換えも有効です。
- 沈黙を尊重する: すぐに答えが出なくても、焦らず待つ姿勢が大切です。
- 問いすぎない: 質問攻めにせず、一つの問いに対してじっくり考える時間、対話する時間を設けます。
- 中立的な立場: ファシリテーター自身の意見や結論に誘導しないよう注意します。
- 肯定的な雰囲気: どんな意見も歓迎し、否定しない雰囲気を作ります。
ファシリテーションの基本的な流れ(5つのフェーズ)
1. 場作り (Set the Stage)
目的: 参加者が安心して発言できる雰囲気を作り、ふりかえりの目的と進め方を確認する。
ファシリテーターの動き: 挨拶、アイスブレイク、目的・ゴールの共有、タイムボックス(時間配分)の説明、グランドルール(例: 批判しない、自由に発言するなど)の確認。
問いかけ例: 「今日はどんな気持ちですか?」「この時間で何を持ち帰りたいですか?」
2. データ収集 (Gather Data)
目的: スプリント期間中に何が起こったか、事実や出来事を客観的に思い出し、共有する。
ファシリテーターの動き: フレームワーク(後述)の各項目について、参加者に付箋などに書き出してもらう。書き出した内容をボードに貼り出し、簡単に共有する(読み上げるなど)。質疑応答は次のフェーズで。
問いかけ例: 「どんなタスクがありましたか?」「印象に残っている出来事は?」
3. アイデア出し・洞察 (Generate Insights)
目的: 集まったデータをもとに、「なぜ」そうなったのか、パターンや原因を探り、気づきや学びを深める。
ファシリテーターの動き: 参加者が書き出した内容について、深掘りする問いかけを行う。関連する項目をグルーピングしたり、議論を促したりする。参加者同士の対話を促進する。
問いかけ例: (上記の問いかけテクニックを活用) 「なぜそう感じたのですか?」「共通点はありますか?」「ここから何が学べますか?」
4. アクション決定 (Decide What to Do)
目的: 洞察に基づき、次のスプリントで試す具体的な改善アクションを決める。
ファシリテーターの動き: 改善アイデアを出し合い、その中から具体的で実行可能なアクションを少数(1〜3個程度)に絞り込む。アクションの担当者や期限を明確にする手伝いをする(例:投票、合意形成)。
問いかけ例: 「この学びを次に活かすには?」「具体的な第一歩は?」「誰がいつまでに試しますか?」
5. ふりかえりのふりかえり (Close the Retrospective)
目的: 今回のふりかえり自体が有意義だったかを確認し、次回の改善につなげる。感謝を伝え合い、ポジティブに締めくくる。
ファシリテーターの動き: ふりかえりの感想や改善点を簡単に共有してもらう(例: ROTI – Return On Time Invested)。感謝の言葉を促したり、ファシリテーター自身も感謝を述べたりする。決定したアクションを再確認する。
問いかけ例: 「今日のふりかえりはどうでしたか?」「次回に向けて何かありますか?」

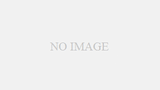
コメント